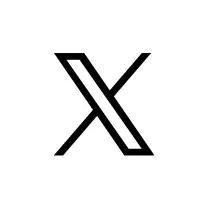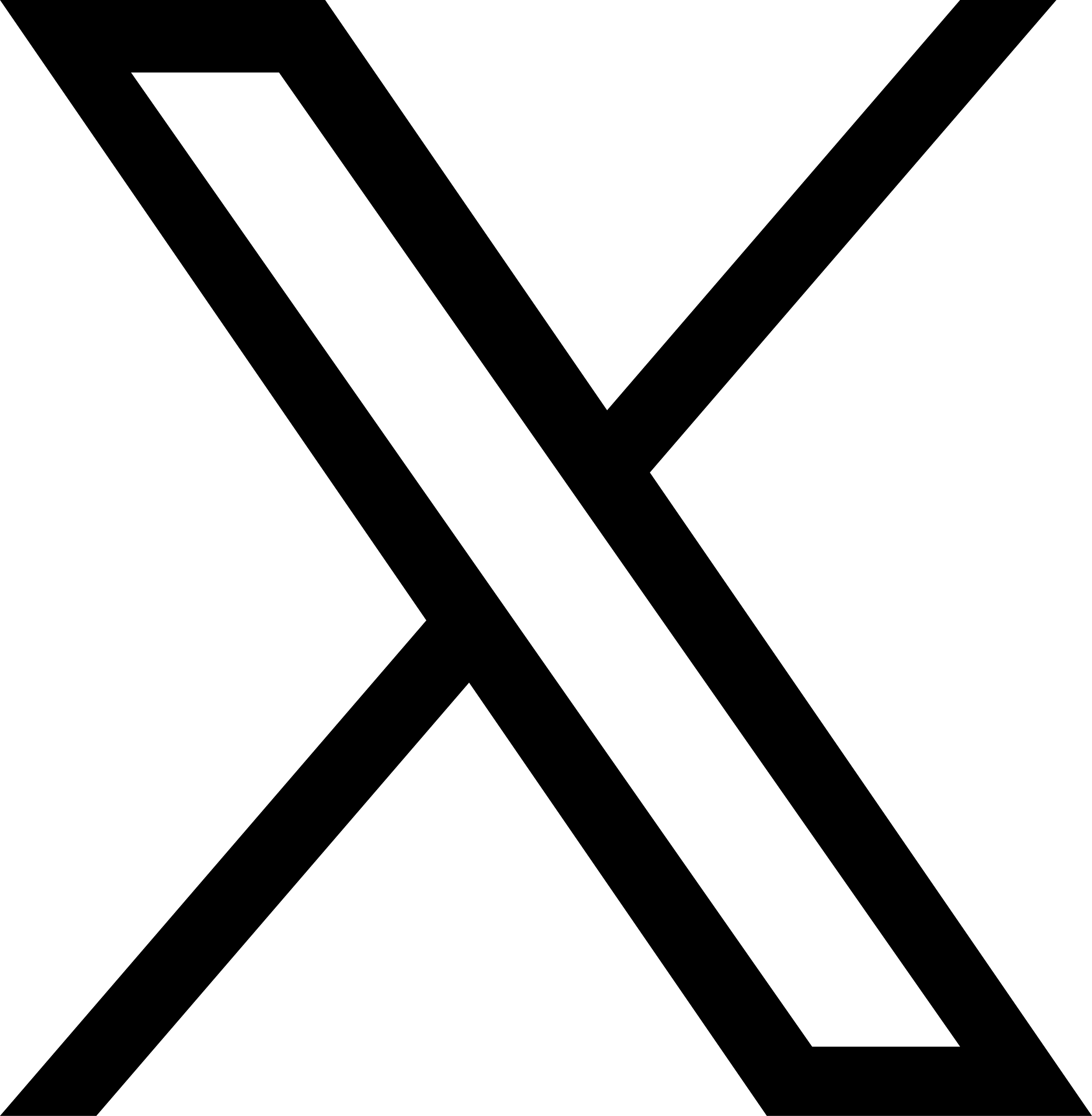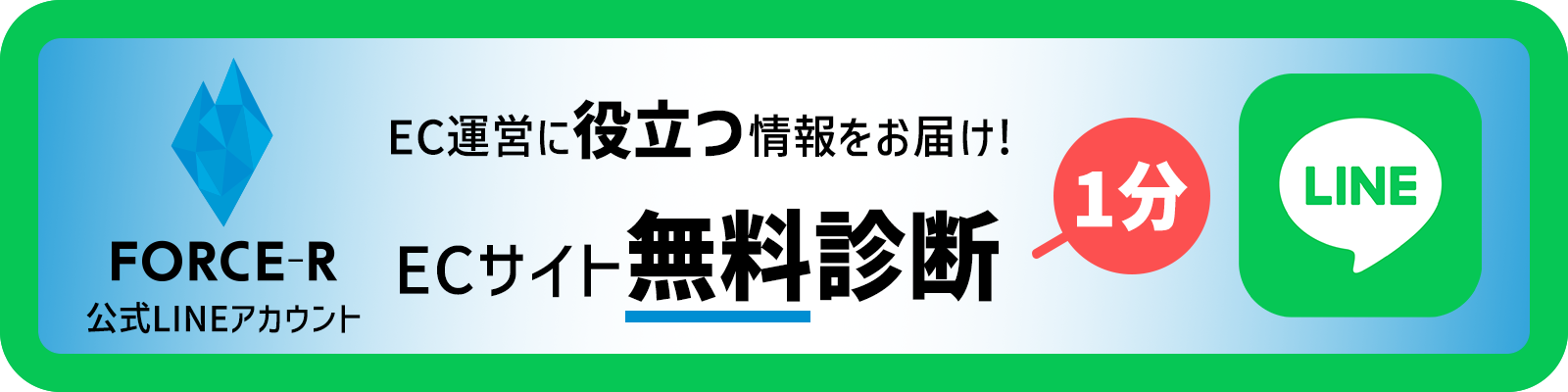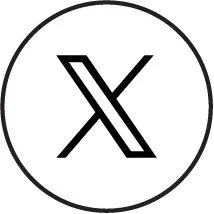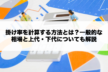「ユニファイドコマースとはどのような施策なの?」
「ユニファイドコマースが注目されている理由が気になる」
「ユニファイドコマースを構築する具体的な方法が知りたい」
このようにお考えではありませんか?ユニファイドコマースは、既存顧客に対して最適なサービスを提供するための施策です。既存顧客の「客離れ」を防いで売上を増やすことで、費用を抑えて利益率を向上させることが可能です。
そこで本記事では、ユニファイドコマースの施策内容から具体的な導入手順まで解説するので、ぜひ参考にしてください。
自社ECサイトの運営で必須な7つのチェックリスト
無料で資料を受け取る

Contents
ユニファイドコマースとは?OMOとの違いも解説

ユニファイドコマースは、複数のチャネルを統合させる「オムニチャネル」や、オンラインとオフラインを統合させる「OMO」と似たような場面で使われることが多いです。しかし、正確には施策の先にある目的がユニファイドコマースの場合は「ユーザー体験の向上」である点が異なります。
そこで、ここではユニファイドコマースの概要について解説します。OMOとの違いも解説するので、ユニファイドコマースへの理解を深めてください。
1. ユニファイドコマースとは
ユニファイドコマースを簡単に説明すると「顧客ごとに最適化された施策」となります。オンラインやオフラインの垣根を超えて、顧客に関する情報を網羅的に調査し、最適なタイミングで提供する施策です。
また、顧客が望むタイミングで最適な商品やサービスを提供することで、ユーザー体験を向上させることが目的となります。ユニファイドコマースは、新規顧客を獲得するためではなく、既存ユーザーの一人ひとりに目を向けて囲い込むマーケティングです。イメージとしては、オムニチャネルとOMOをかけ合わせた施策になります。
オムニチャネルについては、関連記事の「オムニチャネル戦略の5つの効果と実行方法を5ステップで解説【成功事例も紹介】」にて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
2. OMOとの違い
OMOは「利便性の向上」を目的としており、ユニファイドコマースは「顧客体験の向上」を目指している点が異なります。
OMOは「Online Merges with Offline」の略称で、オンラインとオフラインを統合するマーケティングを指します。オンラインとオフラインの壁を取り除き、シームレスにつなぐことで顧客の利便性を高めることが目的です。
ユニファイドコマースにおいても、オンラインとオフラインの垣根をなくす点は同じです。しかし、その後の目的がOMOとは異なります。ユニファイドコマースでは、ユーザー情報の分析を行い、顧客体験を向上させることを目的としています。
簡単にいうと、OMOは顧客が店舗やECサイトへ訪れた際に購入しやすい状況を作る施策です。一方、ユニファイドコマースでは顧客ごとに最適なタイミングや商品を見極め、企業側からアプローチを行います。
ユニファイドコマースの導入が求められる背景

生活スタイルが多様化している現代において、企業が商品やサービスを効果的に宣伝するためには「一人ひとりにあったマーケティング」が重要となっています。ユニファイドコマースが必要とされる背景を理解して「自社も取り入れるべきか」判断していきましょう。
1. カスタマージャーニーの複雑化
スマートフォンが普及し、SNSでの発信が活発化している現代では、カスタマージャーニーが複雑化しています。以前はマスマーケティングが主流で、テレビCMや屋外広告を利用すれば多くの顧客への宣伝が可能でした。
しかし、利用する媒体が複数ある現代において、従来のマーケティング手法だけでは顧客へ効果的な宣伝を行えません。「マスマーケティング」やユーザーの利便性を高めるだけの手法では、成果を上げにくくなっているのが現状です。
また、現代では企業への信頼や愛情を表す「顧客ロイヤリティ」が重要視されています。細分化している顧客ニーズへ「対応する企業努力」をアピールできれば「顧客ロイヤリティ」を高められます。
ユニファイドコマースの実施により顧客一人ひとりを調査し最適な提案を行うことで、さまざまなチャネルからアプローチしてくるユーザーの細かなニーズへ対応していきましょう。
2. 広告費増加による既存顧客の重要性
企業がユーザー獲得のために費やす広告費は、以下のグラフのとおり増額傾向です。

2020年はコロナ禍の影響で一度下がっていますが、2022年では過去最高額を記録しています。
また、アメリカのコンサンティング会社「Bain & Company」のフレデリック・F・ライクベルト氏は「1:5」の法則を提唱しています。「1:5」の法則とは「新規顧客の獲得には多額の費用が必要であり、既存顧客の維持よりも5倍の費用がかかる」という法則です。
実際に、企業が自社サービスの宣伝を行うために費やす広告費は、年々増加しています。そのため、企業としては「新規顧客を獲得する」のではなく「既存顧客を囲い込む」ほうが効率よく利益を上げられるでしょう。
そのため、既存ユーザーへパーソナライズされたサービスを提供する「ユニファイドコマース」が注目されています。
ユニファイドコマースを導入する手順3ステップ

ユニファイドコマースを実施するために何から始めれば良いか、わからない方が多いのではないでしょうか。こちらでは、ユニファイドコマースを導入する手順を3つのステップで説明します。
実現までの過程を事前に把握することで準備するべきことがわかり、問題がある場合は前もって対策が可能です。
1. 土台の設計
ユニファイドコマースを展開するためには、まず土台である「オムニチャネル」の仕組みが必要です。オムニチャネルは、オンラインやオフラインはもちろん、SNSなどを含めたすべての経路を統合するマーケティング手法です。
オムニチャネルを実装するには、在庫や顧客情報を管理しているシステムを1つにまとめる必要があります。そして、各チャネルと「認識」や「情報」を共有しておき、シームレスにつながれる状況を作り出すことが重要です。
この仕組みがユニファイドコマースには必要不可欠であり、オムニチャネルで得た情報をもとに、サービスを顧客ごとに最適化していきます。ユニファイドコマースを実施するためには、まずシステムの統合や情報共有からはじめましょう。
2. 徹底的なデータ分析
サービスを個々の顧客へ最適化するには、行動履歴や購入履歴を徹底的に調べなければなりません。「個人」一人ひとりに焦点を当てて、最適なアプローチ方法を見いだしましょう。
例えば、ユーザーの購入品傾向が把握できれば、それをもとにおすすめ商品を提示できます。また、日用品など消耗品をよく購入しているユーザーであれば、在庫が切れるタイミングで購入を促す通知を配信できます。
データ分析の精度によってユニファイドコマースの成果は影響されるため、データ分析チームの発足や専門的な人員を配置して、徹底的に顧客情報を掘り起こしましょう。
3. 顧客別に最適なアプローチを実施
データ分析から見いだした、最適なアプローチを継続していくことが「ユニファイドコマース」です。1人のユーザーに対して、情報分析による最適なサービスを提供していくことで、顧客体験の向上につながります。
他社との差別化を図れるとともに「企業が自分のことを理解してくれている」とユーザーに好意的に受け止められるため、購買意欲の向上が期待できます。
例えば、ユーザーがよく購入している商品やブランドで利用できる「クーポン」を配布すれば、CV率やクリック率の向上が可能です。一方で客単価を下げることにもつながるので、割引率はもちろんタイミングや頻度にも注意しましょう。
ユニファイドコマースにおける5つの課題

ユニファイドコマースを適切に実現できれば、既存ユーザーの囲い込みが可能です。また、自社商品を継続して購入してくれる「生涯顧客」にもなり得るでしょう。
ただし、ユニファイドコマースを実施するには多くの課題があります。この章の内容を確認して、直面するであろう課題を事前に把握しておきましょう。
1. データ統合の難しさ
ユニファイドコマースを実現するためには、まず土台であるデータの統合が必要です。しかし、社内の複数のシステムに情報が分散されているケースは多いため、データの統合は容易ではありません。
ユニファイドコマースは、統合されたデータをもとに顧客情報を徹底的に分析し、最適なサービス提供をしていきます。データの統合を行い企業内の情報を整理するため、システム統一にかかる費用や技術的な課題を解決していきましょう。
2. 適切な顧客セグメント
ユニファイドコマースにおけるセグメントとは、顧客を年齢や性別などで分類することを指します。高い精度で顧客の分類を行わなければ、その先の最適なサービス提供につなげることはできません。
ユニファイドコマースでは「一人ひとりに最適なアプローチ」を行います。しかし、実際に個々の分析に時間をかけていては運営が成り立ちません。そのため、似た特徴を持つユーザーの絞り込みがとても重要で、その振り分けを行うのが「セグメント」の工程です。
3. サービスやコンテンツの不足
ユニファイドコマースでは、ユーザーごとに最適なアプローチを行うため、豊富なコンテンツが必要です。いくら最適なアプローチを見いだしても、ニーズを満たす商品やサービスがなければユーザーへ提示できません。
顧客のセグメントと同時に、コンテンツの種類も増やしていきましょう。そのためには、商品開発やサービスの選定に注力する必要があります。顧客ニーズに合わせて既存商品の一部機能をアレンジしたり、ユーザーへの提供方法を変化させたりして対応していくことが重要です。
4. ユーザーに対する「安心感」の提供
ユニファイドコマースでは、企業側からユーザー側へ最適なサービスを提案していきます。その際に重要となるのが「安心感を合わせて提供すること」です。
提案を受け取るユーザーの中には、機械的な分類や提案を受けることに、嫌悪感を持つ方が一定数います。例えば、最適なアプローチであったとしても「機械的な自動配信」は冷たく感じるため「実店舗のスタッフからの配信」を実施してみるなどです。
顧客が利用したことのある店舗があれば、そこから配信を行うことでより安心感を感じやすいです。また、丁寧さや信頼を感じられる提案を行うことで、ユーザーは安心感を覚えます。
5. 商品在庫の管理
ユニファイドコマースにおいては、商品在庫の管理をより一層徹底しなければなりません。ユーザーへ最適なアプローチを寄せるユニファイドコマースでは、人気商品を大量に仕入れるより、幅広く仕入れを行うことが重要です。
ユーザーニーズを満たす商品が不足しないように、ECサイトと実店舗の在庫管理システムを統合し、シームレスな管理体制を築くことが必要です。
ユニファイドコマースを成功させたいならFORCE-R

ユニファイドコマースでは、土台である「オムニチャネル」の構築から情報分析による最適なサービス提供まで、多くの工程が必要です。
FORCE-Rのコンサルティングでは、クライアント様の状況に応じて必要な施策を提案させていただきます。また、弊社所属の経験豊富なコンサルタントが専属で御社の事業をサポートいたします。
さらに弊社では、業界初(※弊社調べ)の「定量×定性」分析を行っており、消費者目線での課題発見が可能です。ご興味を持たれた方は、以下のリンクよりお気軽にお問い合わせください。
まとめ|ユニファイドコマースで顧客ごとに適した施策を実行しよう
ユニファイドコマースの目的は、顧客それぞれのニーズを満たすために最適化したサービスや商品を提供して、ユーザー体験の向上を図ることです。カスタマージャーニーが複雑化している現代において有効な施策といえるため、実現できれば顧客満足度の向上が期待できます。
ただし、ユニファイドコマースを実現するには、システム統合からデータ分析まで幅広い施策や企業内でのデータの共有が必要です。FORCE-Rへご依頼いただければ、ユニファイドコマースの実現を専門的な知識のもとでサポートさせていただきます。