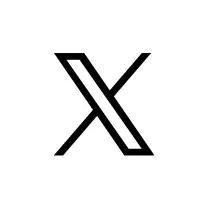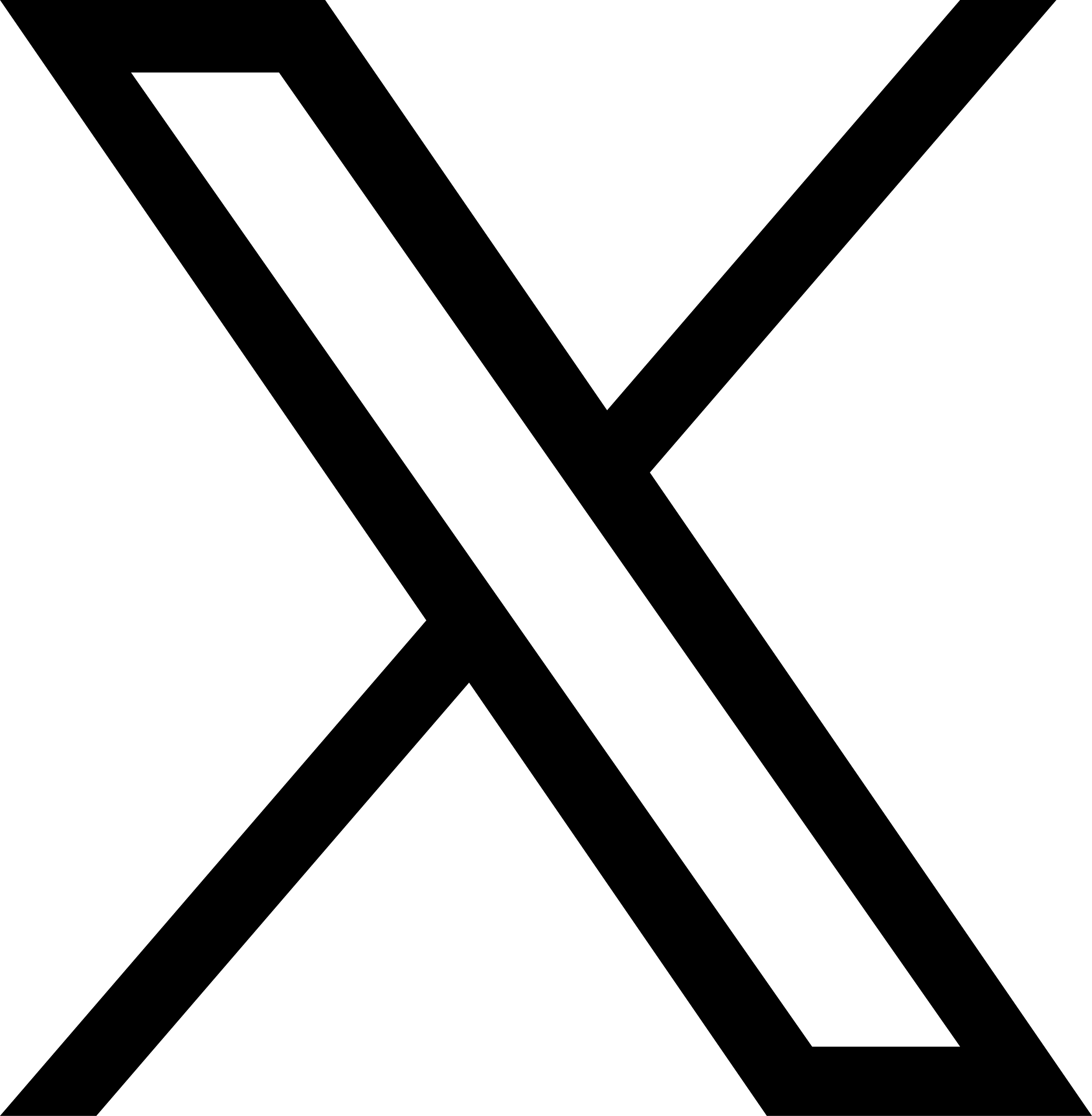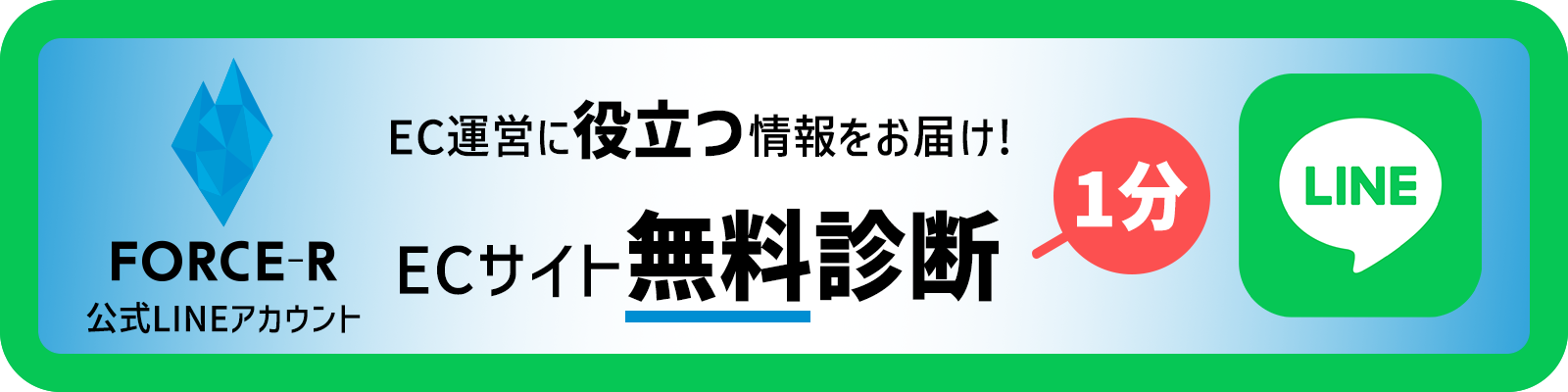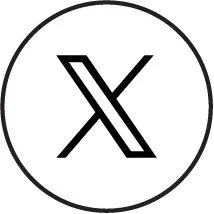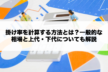「ECサイト運営でセキュリティ事故が起きる原因を知りたい」
「ECサイトに有効なセキュリティ対策を教えてほしい」
「情報漏洩のリスクに備えたい」
ECサイトのセキュリティ対策に関して、上記のような疑問や課題を持っていませんか。顧客や社内の情報漏洩、ページの改ざんよってECサイト運営を継続できなくなる可能性があるため、セキュリティ対策は必須です。
そこで本記事では、ECサイトでセキュリティ対策が必要となる背景や事故が発生する要因、具体的な対策方法を解説します。ECサイトでセキュリティ事故が発生した場合のリスクも理解できる内容になっているので、ECサイトの運営担当の方はぜひ最後までお読みください。
自社ECサイトの運営で必須な7つのチェックリスト
無料で資料を受け取る

Contents
ECサイトで発生するセキュリティ事故について解説

セキュリティ事故とは、企業や組織が保有する情報の漏洩や消失が起こることを指します。ECサイトにおけるセキュリティ事故の例は、以下のとおりです。
- クレジットカードの不正利用
- 迷惑メール
- マルウェア感染
- 不正アクセス
- サイトの改ざん
クレジットカード情報が漏洩して不正に利用されたり、サイトが改ざんされて虚偽情報が記載されたりする被害が起きています。またマルウェア感染とは、デバイスを攻撃する悪意のあるプログラムやソフトウェアがECサイトに入り込むことです。感染することによって情報の抜き取りやスパムメールの配信、データ破壊といった被害にあう恐れがあります。
ECサイトでセキュリティ対策が必要となる背景

2023年、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と経済産業省が連携してECサイト構築・運用セキュリティガイドラインを公開しました。ECサイトの構築や運営を行う中小企業向けに作成されており、国を挙げてセキュリティ対策に乗りだしていることがわかります。
一方で、セキュリティ対策の重要度を理解していないままECサイトを運営している方は多いです。ここでは、ECサイト運営にセキュリティ対策が求められる背景を見ていきましょう。
1. クレジットカードの不正利用被害額が増加している
社団法人日本クレジット協会のクレジットカード不正利用被害の発生状況によると、2023年の不正利用による被害額は540.9億円でした。2014円は113.9億円でしたので、10年で400億円以上も増加しています。
特に番号盗用による被害額が大幅に増加しており、2014年は全体の58.6%でしたが、2023年は93.3%を占める結果となりました。ECサイトからクレジットカード情報を抜き取られたケースもあるため、運営者には不正利用対策を徹底することが求められています。
2. 個人情報の漏洩・紛失事故が増加している
東京商工リサーチの2023年上場企業の個人情報漏えい・紛失事故調査によると、2023年の漏洩・紛失事故の件数、漏洩した個人情報は2022年よりも増加しました。事故件数と情報漏洩人数は調査を開始した2012年以降で過去最多を記録しており、3年間右肩上がりとなっています。
増加する個人情報の漏洩・紛失事故を防ぐために、ECサイトにもセキュリティ対策が必須です。
セキュリティ事故が発生する3つの要因

原因がわからない状態で対策を行うのは難しいため、まずはセキュリティ事故の要因を理解する必要があります。ここでは、セキュリティ事故が発生する要因を3つ説明します。
1. 外部からの攻撃を受ける
悪意のある第三者がアプリやシステムの脆弱性を狙い、ECサイトを攻撃することがあります。インターネット経由でパソコンやサーバーの情報端末に不正アクセスし、システムの破壊や改ざん、窃取をおこなうサイバー攻撃が有名です。
特にデータを盗んだ企業に対し、データの公開と引き換えに対価として金銭の支払いを求める二重脅迫の被害が増えています。外部からの攻撃によって、ECサイトが受ける被害は以下のとおりです。
- クレジットカードや住所、購入履歴などの個人情報が流出する
- ECサイトのページが書き換えられる
- システムを破壊されてECサイトが利用できなくなる
ECサイトにセキュリティ上の欠陥があることで、サイバー攻撃による被害を受けやすくなります。
2. ECサイトの関係者が不正する
ECサイトの関係者が不正を働いて、意図的に情報を持ち出されることもあります。ECサイト内部の人は、サイバー攻撃の知識がなくても簡単にデータを抜き出すことが可能です。関係者の不正によって抜き出されたサイトの重要情報や個人情報が、悪用される例は以下のとおりです。
- 売上や利益率といった自社情報を抜き取って競合他社へ公開する
- 転売目的で顧客情報を流出させる
従業員が企業に不満を感じていたり、データ管理がずさんになっていたりする場合、内部不正によるセキュリティ事故が発生するリスクが高まります。
3. ヒューマンエラーが発生する
悪意のない人がミスをした場合でも、データの破壊や漏洩といったセキュリティ事故が起こり得ます。セキュリティ事故の原因となる従業員のミスは、以下のとおりです。
- 顧客情報が記録された書類を誤送信する
- ノートパソコンやUSBメモリを外出先に忘れる
- 操作を誤ってファイルを削除する
またクレジットカード情報が盗用されることによって、顧客が不正利用の被害にあうケースもあります。ヒューマンエラーにより、セキュリティ事故が発生する可能性があることを理解しておきましょう。
ECサイト運営で取り組むべき5つのセキュリティ対策

ECサイト運営では、外部からの攻撃・内部不正・ヒューマンエラーに備えたセキュリティ対策が必要です。ここでは、ECサイト運営で取り組むべきセキュリティ対策を解説します。
自社でまだ取り組んでいないセキュリティ対策がないか、チェックしながら読み進めてください。
1. アプリやシステムを最新バージョンにアップデートする
ECサイト運営に使用するアプリやシステムは、更新の際に旧バージョンで見られた脆弱性を解消しています。悪意のある第三者からの攻撃を防ぐために、アプリやシステムを最新バージョンにアップデートするようにしましょう。
ECサイトを手軽に構築できるASPカートを活用していれば、サービス提供者が定期的にアップデートを行ってくれるため、漏れがなくて安心です。
ASPカートについては関連記事の「ASPカートとはECサイトの構築システムを提供するサービス!導入効果とおすすめを紹介」で説明しているので、ぜひ参考にしてください。
2. 安全性の高いパスワードを使用するように義務付ける
顧客がECサイトのログインに使用するパスワードは、安全性の低いものは設定できないルールにしましょう。推測しやすい簡単なパスワードを使用できないため、第三者が顧客のアカウントにログインすることが難しくなります。安全性の高いパスワードの特徴は、以下のとおりです。
- 英字・数字・記号をすべて含んでいる
- 大文字が使用されている
- 10文字以上で構成されている
- 「password」のような意味のある文字列になっていない
しかし、ルールが複雑過ぎるとユーザーが入力を面倒に感じて会員登録をやめてしまう可能性はあります。また購入時にパスワードを忘れたりすることによる、新規顧客数の減少やカゴ落ちのリスクにも注意が必要です。
カゴ落ちについては関連記事の「カゴ落ちとはカートに入れた商品を購入せず離脱されること!サイトを離れる理由と対策を紹介」にて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
3. セキュリティポリシーを策定する
セキュリティポリシーとは、企業や組織が実施するセキュリティ対策の方針です。セキュリティポリシーを策定しておくことで、情報資産に関する従業員の意識を統一できます。セキュリティポリシーに記載すべき内容は、以下のとおりです
- セキュリティ対策を行う目的
- 対策を進める際の基本方針
- 基本方針を実践するために必要な具体的な規則
- セキュリティ対策の実施手順
IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の中小企業の情報セキュリティ対策ガイドラインや総務省が公開している国民のためのサイバーセキュリティサイトを参考にして、セキュリティポリシーを作成しましょう。
従業員がセキュリティポリシーを把握していないと対策が不十分になりやすいので、共有を徹底してください。また、セキュリティポリシーの公開は情報管理を徹底しているアピールにつながるため、ユーザーからの信頼に繋がります。
4. 不正アクセスを検知するサービスを導入する
ウイルスの侵入やサイバー攻撃に気付くのは難しいため、不正アクセスを検知するサービスの導入がおすすめです。ECサイトで利用できる不正アクセス検知サービスには、以下のようなものがあります。
サービスを導入することで、ECサイトにおける不正な挙動を検知してセキュリティ事故を未然に防げます。
5. セキュリティテストを実施する
定期的にセキュリティテストを実施することにより、ECサイトにセキュリティ上の欠陥がないかを確認して修正可能です。ECサイトで利用できる脆弱性検査ツールは、以下のようなものがあります。
セキュリティテストとして一般的な脆弱性診断を活用すれば、悪意のある第三者が脆弱性を狙ったサイバー攻撃を行った際に、セキュリティ事故が発生するリスクをチェックできます。
ECサイトのセキュリティ事故によって発生する事業リスク

セキュリティ事故によって「ECサイト運営にどのような影響があるか」を理解できていない方は多いです。ここでは、ECサイトのセキュリティ事故によって発生する事業リスクを紹介します。
事故が起きてから後悔しないよう、事前にリスクを把握してセキュリティ対策の重要性を理解しておきましょう。
1. 個人情報の流出によって賠償金の支払い義務が発生する
セキュリティ事故が起きて個人情報が流出することで、ECサイトに賠償金の支払い義務が生じるケースがあります。過去の事例から見ると、個人情報の流出による1人当たりの賠償金額は5,000〜1万円程度が相場です。
被害人数に合わせて賠償金額が大きくなるため、約5万人の個人情報が流出した際に5億円以上を支払った事例もあります。セキュリティ事故の賠償金やECサイトの修正費用、事故の調査費用を支払ったうえで、顧客からの信頼を失って売上が大幅に減少するリスクを理解しておきましょう。
2. 顧客離れが起きて売上が減少する
セキュリティ事故を起こしたECサイトに対して顧客は不信感を抱くため、売上が減少します。顧客離れの原因になり得る信頼の失墜を防ぐために、速やかに以下の行動を取りましょう。
- 情報漏洩が起きたことを発表する
- 顧客に対して謝罪する
- 対策をしてセキュリティを強化する
対応が悪ければ、顧客はさらなる不信感を抱く恐れがあります。そのため、セキュリティ事故が発生しても従業員が冷静に適切な対応ができるように、セキュリティポリシーを定めておきましょう。
ECサイトのセキュリティ対策を行うならFORCE-R

クレジットカードの不正利用被害や個人情報の漏洩・紛失事故が増加しており、ECサイトにもセキュリティ対策が求められています。ただしセキュリティ事故には、外部からの攻撃・内部不正・ヒューマンエラーと多くの要因があるので、それぞれに合わせた対策が必要です。
FORCE-Rでは、専門コンサルタントがECサイトのセキュリティ対策をサポートします。「自社サイトのセキュリティ対策が十分であるか不安」とお悩みの方は、ぜひFORCE-Rへご相談ください。過去の運用実績などの所定の条件を満たした者のみをコンサルタントに起用しているため、専門知識を活かした質の高いセキュリティ対策を実行可能です。
まとめ|ECサイトの情報漏えいを防ぐにはセキュリティ対策が重要

セキュリティ事故によって、賠償金の支払い義務が発生したり、顧客が離れて売上が減少したりする恐れがあります。安定的にECサイト運営を継続するためには、セキュリティ対策が欠かせません。
ただ「具体的に何に取り組むべきかわからない」「事故が起きていないのでこのままで大丈夫」と着手できていない企業は多いです。自社ECサイトのセキュリティ事故に対策したい方は、お気軽にFORCE-Rへご相談ください。経験豊富なコンサルタントが、ECサイトに合わせたセキュリティ対策をサポートいたします。