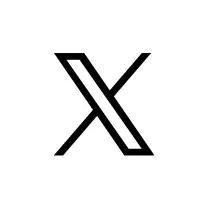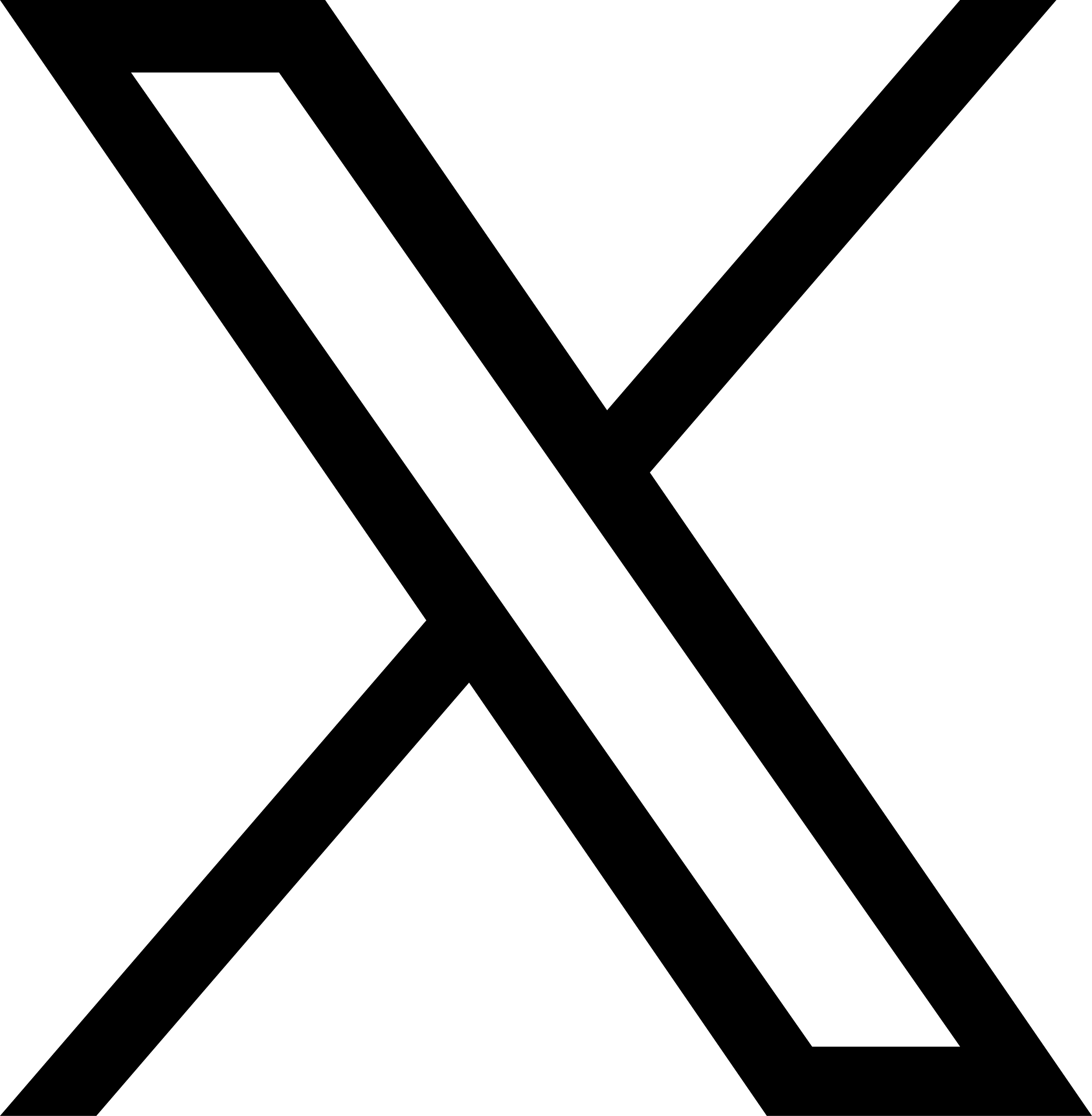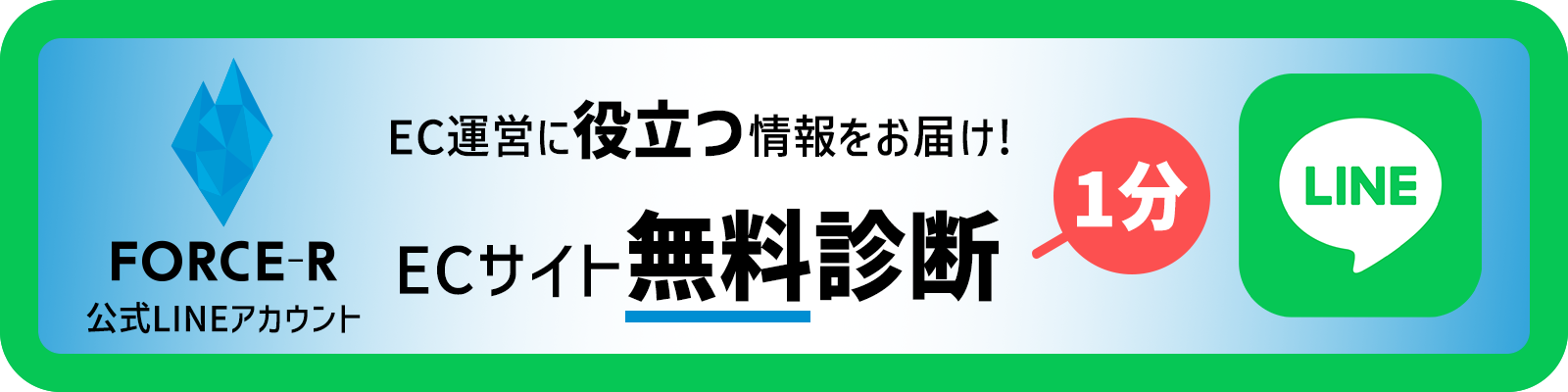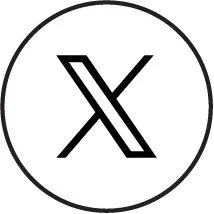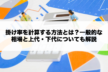「O2O、OMO、オムニチャネルといった用語の違いがわからない」
「OMOを導入するメリットや活用方法が知りたい」
「他社の成功事例を自社に取り入れたい」
このようなお悩みをお持ちではありませんか。インターネット上で気軽に買い物ができるようになった現代において、集客やマーケティング施策はオフラインの対策だけでは不十分です。
本記事では、オンライン施策を通じて店舗へ誘導するO2Oや購買体験の向上を目的としたOMOの特徴や違いについて詳しく解説します。施策を成功させるポイントや事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。O2OやOMO施策を活用して、売上アップを実現しましょう。
自社ECサイトの運営で必須な7つのチェックリスト
無料で資料を受け取る

Contents
O2OとOMOの特徴と違いについて解説

O2OとOMOは似た用語ですが、オンライン施策の役割が異なります。O2Oの考え方を発展させたものがOMOであり、オンラインとオフラインの双方の強み・弱みを相互補完することで、顧客により良い購買体験を提供する施策です。
それぞれの特徴や違いを説明するため、自社で行うべき施策はどちらが良いかの判断材料として活用してください。
1. O2Oの特徴
O2Oとは「Online to Offline」の略語であり、オンラインを通してオフラインへ誘導するための施策です。オンラインは実店舗へ誘導するための手段として活用します。
例えば、メルマガやLINEを使ったオンライン上でクーポンを配信したり、セールの告知を行ったりすることで、実際の店舗に集客を行う施策があげられます。
2. OMOの特徴
OMOは「Online Merges with Offline」の略語で、オンラインとオフラインを融合させる施策を指します。オンラインとオフラインの垣根を超え、購買体験をシームレスに行えることを目的にしている「顧客視点のマーケティング戦略」です。
従来は店舗での買い物とECサイトでの購入は、データの連携やクーポン施策などもない独立したものでした。OMOは近年のインターネットやスマートフォンの普及により、オンラインとオフラインの境目がなくなってきたことから生まれた施策です。
OMOでは、O2Oと同様にクーポンを配布して送客を行います。さらに実店舗でもアプリやECサイトを紹介し、オンラインでの購入も同時に促します。このように、顧客にとって一番便利な方法を提供していく施策がOMOです。
3. O2OとOMOの違い
O2Oはオフラインでの集客・販売が軸であり、オンラインは送客の手段として、明確に切り分けて考えます。一方OMOでは、オンラインとオフラインの区別をせず、双方のメリット・デメリットをカバーし合うことで、顧客にとって最適な購買体験を提供することが目的です。
購買体験の向上を目的としているため、購入からアフターフォローまでをオンライン・オフラインのいずれかに限定することなく、顧客にとって最適な方法で行います。
O2OやOMOと似た施策であり、実店舗やアプリ、SNSなどさまざまな媒体をデータ連携させるオムニチャネルについては関連記事の「オムニチャネル戦略の5つの効果と実行方法を5ステップで解説【成功事例も紹介】」にて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
OMO施策を行う3つのメリット

OMO施策を導入することで、購入に至っていなかった顧客へのアプローチが可能になり、売上アップの機会損失を防げます。また顧客ニーズがデータとして取れるため、より良い購買体験の提供ができ、リピーターを増やすことにもつながります。
集客数の増加や売上の向上につながる施策となり得るため、ぜひ参考にしてください。
1. 機会損失を防げる
OMO施策を導入することで、顧客が購入に迷った際に不安を解消したり、その場では買わずとも適切なタイミングでリマインドできたりします。顧客が買わない判断をする理由に先回りして対策しておくことで、機会損失を防ぐことが可能です。
例えば、店頭で購入を悩んだ際に口コミやコーディネート事例を紹介することで購入の後押しができます。また、店頭での購入履歴を元におすすめの商品をオンライン上で広告することで、他店舗へ流入してしまうリスクも減らせます。
ECサイト上でカートに入れたまま購入していない方へ、リマインドすることでカゴ落ちを防ぐ施策も可能です。
カゴ落ち対策については関連記事の「カゴ落ちとはカートに入れた商品を購入せず離脱されること!サイトを離れる理由と対策を紹介」にて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
2. 顧客ニーズを把握できる
オフラインとオンラインのデータを統合することで、好みや購入時期など顧客ニーズが把握できるようになります。ニーズに合わせた新商品や買い替えの提案を行うことで、顧客の購入意欲を高められます。
データ収集・分析の精度を高めるためには、オンライン・オフラインの双方で接点数を増やし、適切に各要素を統合できるように収集・連携方法を工夫しましょう。具体的には「顧客IDのひもづけで購入履歴が一元化できる」「常に最新の店頭在庫がオンライン上でも見れる」といった例があげられます。
顧客満足度を上げるだけでなく、商品開発やサービス向上のデータとしても活用できる点もOMO施策のメリットです。
3. 顧客生涯価値の最大化
売上を上げるためには、単価を上げるだけでなく継続的に購入してくれる顧客の数を増やすことも重要です。顧客が今後自社にもたらす収益を表す指標を、顧客生涯価値(LTV)と呼びます。
OMOは顧客の購買体験をより良くするための施策です。顧客の体験価値が高まることで、自社のファンが増え、結果としてリピーターも増加します。ファンやリピーターがすぐに増えることはないため、中長期で顧客体験価値を高めていくことでLTVの増加へつなげていきましょう。
OMO施策を成功させる3つのポイント

OMO施策は売上アップの機会損失を防ぎ、顧客へより良い購買体験を提供することを可能とします。ただし、成功させるためには仕組みや配置など適切な準備が欠かせません。
この章で紹介するポイントを導入を検討する際の参考にしてください。
1. データ収集数の増加と一元管理
顧客の行動を元にしたデータを分析・活用するためには、大元となるサンプル数が大切です。そのため、まずは顧客接点量を増やしましょう。
クーポンやイベント通知を用いてオンライン・オフラインで相互に送客し合う仕組みを作ることや、SNSや広告で新規顧客を集客を実施することで接点数が増えていきます。
顧客接点を取る際は、満足度の向上を目的とするのであれば「接客や配送」「商品の品質の評価」など、あらかじめ分析したいデータが取得できるようにしましょう。オンラインとオフラインのデータが紐づくよう、同一IDで管理することも忘れないようにしてください。
2. 施策展開を行える担当者や部署の配置
OMO施策を行う際には、オフライン(実店舗)とオンライン(ECサイトなど)の双方の業務理解が欠かせません。両方の視点を意識しながら戦略を考えるためです。データを集めて分析し、新しい施策に活用していくためにはマーケティングや分析などさまざまなスキルが必要になります。
そのため、施策の立案から遂行まで行う専門の担当者や部署を配置することが重要です。さまざまな部署や人員と連携することも多いため、利害関係や進捗を調整する能力もあるとなお良いでしょう。
3. 顧客体験をもとにした施策検討
顧客の購買体験をより良いものにする施策がOMOです。そのため、顧客視点に立って施策を考える必要があります。まずは「顧客が便利だと思っていること」「使いづらいと思っていること」など良い点・悪い点の両方を洗い出しましょう。
例えば支払い方法について「コストがかかる」といった企業目線だけではなく、顧客の利便性向上のため自由に選択できるような複数の決済方法を導入します。顧客目線で改善すべき施策を決めていくことで、購買体験の向上につながります。
OMO施策の成功事例

ここでは、OMO施策で売上を上げた実例を紹介します。成功している事例には理由があります。自社で取り入れられるポイントを意識し、積極的に活用していきましょう。
1. サントリー
サントリーが行っている「TOUCH-AND-GO-COFFEE」では、LINEチャットで自分好みのコーヒーを注文でき、指定した時間に店舗で受け取れるサービスを展開しています。
店舗でカスタマイズを行う場合は、後ろに他のお客様もいる場合に時間をかけて決めることは難しいです。しかし「TOUCH-AND-GO-COFFEE」では、落ちついた環境で自分好みのコーヒーを選べます。
また、5分単位で受け取る時間を指定でき、ロッカーに置いてある商品を回収するだけのため、待ち時間を減らせる点も魅力の1つです。店舗側としても事前にオーダーを受けるため余裕を持ってドリンクを作れる点や、非接触でサービスを行える点が生産性アップにつながっています。
2. ニトリ
家具やインテリア用品を販売するニトリでは「ニトリのリフォーム」というサービスにて、ビデオ通話を活用した接客を実現しています。
「LiveCall」というビデオ通話を用いることで、自宅にいながら商談を行えるようになりました。実際にリフォームしたい箇所を事前に見せながら会話ができるため、双方のイメージを共有しながら話が進められる点がメリットです。このような取り組みにより、担当者が行うアドバイスも的確になります。
店舗に何度も通う必要もなくなるため、遠方に住んでいる方にも魅力的です。また、ショールームにはタブレットを置いておき、接客中で担当者が手を離せない場合には、余裕がある別店舗の担当者と電話できるような工夫も行っています。
3. フーマーフレッシュ
フーマーフレッシュはアリババグループで、中国で200店舗以上を展開しているスーパーマーケットです。オンラインで購入した場合は、3km圏内であれば30分以内に無料で配送してもらえます。
実際に店舗に行って実物を確認しながら、アプリで読み込むことで指定時間に自宅に商品を届けてもらうことが可能です。商品を持ち歩かなくて良いため、時間が空いたときに気軽に買い物ができます。
また、店舗に訪れた際にスマホでバーコードを読み取ると、以下のような情報が表示されます。
- 商品在庫
- 産地
- 調理方法
- 口コミ・レビュー
このような情報を店舗で得られるため、買い物の利便性が高まります。オンラインとオフラインのそれぞれのメリットがあり、ライフスタイルやその日の予定に合わせて使い分けできる点が魅力です。
機会損失を防ぐOMO施策を実行するならFORCE-R

OMOは顧客の購買体験の価値を高めることで機会損失を防ぎ、リピーターを増やしていく施策です。ただし、施策を行う際にはオンラインとオフラインの両方の実務やマーケティングに精通し、なおかつ各部署と連携をスムーズに取れる人材が欠かせません。
自社に適切な人材がいない場合は、育成するか新たに採用する必要があります。しかし、育成にも採用にも時間とコストがかかり、確実に成功する保証はありません。もし、自社に適切な人材がいない場合にはEC業界に精通した企業にお任せすることをおすすめします。
FORCE-RであればOMO施策導入のサポートだけでなく、将来的に自社の人材で続けていくための支援も実施しています。
まとめ|OMO施策はデータ収集と顧客目線の施策が重要
OMO施策を成功させるためには、適切な人材のもとで活用しやすいデータ収集と顧客視点に立ったアイディアの両方が重要です。顧客満足度を高めるために効果的な施策ですが、人材の確保や企画・実行など自社で全てを行う難易度は高いです。
初めてOMO施策を行う際は、プロの力を借りることをおすすめします。FORCE-RであればOMO施策の導入はもちろん、企画立案・改善など結果がでるまでサポートが可能です。「顧客が商品を購入する際の体験価値を高めたい」と考えている企業担当者の方は、お気軽にFORCE-Rにお問い合わせください。